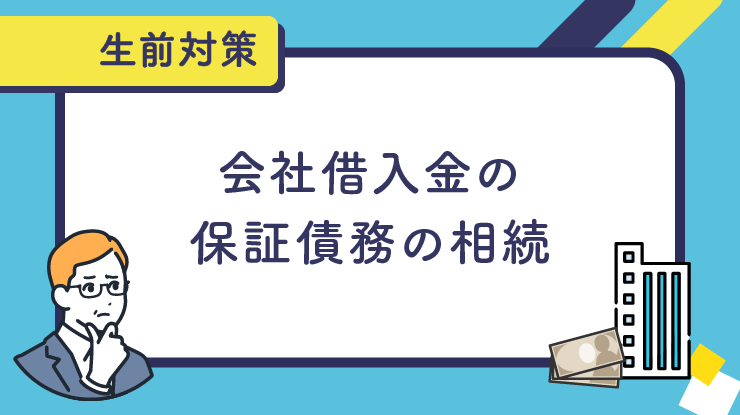今回は、中小企業経営者が抱える会社借入金の保証債務リスクを取り上げ、生前対策や相続放棄、M&A などによる解決策を解説します。後継者の不在に悩む方々の事業承継にも役立つ内容です。
\専門性高く幅広いニーズに素早く対応!初回無料相談はこちらから/
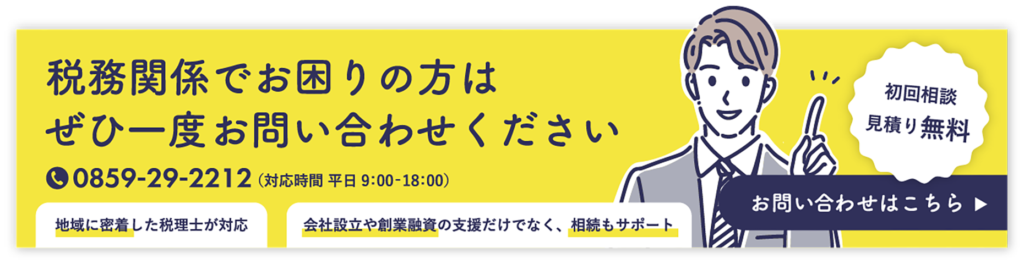
経営者にとっての保証債務の相続リスク
中小企業の経営者が、会社の借入金に対して、経営者個人で連帯保証を行うことは珍しくありません。これを経営者保証、保証債務といいます。
中小企業が資金調達を行うために金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結する際、経営者個人の連帯保証を求められることが一般的で、会社が返済不能に陥った場合、経営者個人の資産をもって返済しなければなりません。
経営者が突然の事故や病気で亡くなった場合、保証債務は一つの債務として相続財産に含まれるため、相続人はその返済責任を連帯して負うことになります。
相続人の中に会社の後継者がいるならば、事業を継続する中で返済を続けることが可能かもしれません。
しかし、後継者が見当たらない場合や、会社の業績が不安定な場合には、相続人が予期せぬ債務を抱えることになりかねません。
後継者が決まっていない段階で経営者が急逝し、保証債務が相続されると、相続人全体で多額の返済義務を負うリスクが生じます。
こうした事態を回避するため、経営者としては生前に保証債務を見直し、可能な限り整理しておくことが必要です。
金融機関との交渉による保証解除や、借入金を減らす、M&Aによって会社を譲渡し、保証債務も引き継いでもらうといった選択肢が考えられます。
ただし、会社のM&Aは、対象となる事業の財務状況や収益性に左右されるため、必ずしもすべての企業がM&Aに成功できるわけではありません。M&Aを行うことができなければ、相続人が承継せざるを得ません。
相続放棄の基本と手続きの流れ
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を一切引き継がないことを意思表示する法的手続きのことです。
これによって、保証債務も含めたすべての資産・負債から離脱することができます。相続放棄が認められると、法律上「はじめから相続人ではなかった」扱いとなります。
もっとも、相続放棄をするとプラスの財産も一切取得できなくなる点には注意が必要です。
自宅の土地や建物などの不動産、預貯金、有価証券などのプラス財産まで相続できなくなるため、どの程度の相続財産があるかを事前に確認したうえで検討することが大切です。
相続放棄を行う手続きは、相続財産の調査から始まります。金融機関や関係先に問い合わせを行い、被相続人名義の口座残高や借入金の残高、保証契約の有無などを確認します。
その次に、相続放棄を行うか否かを判断します。相続放棄には期限があり、被相続人が亡くなった事実を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して申述の手続きを行わなければなりません。
相続放棄を申し立てる際には、相続放棄申述書や被相続人と申述人の戸籍謄本など、必要書類を所定の形式で提出します。
その後、家庭裁判所から照会書が送られてくることがあります。
照会書には、相続放棄の意思が真実かどうかを確認する質問が記載されており、回答を記入して返送することになります。問題なく手続きが進めば、相続放棄申述受理通知書が交付され、相続放棄が認められることになります。
相続放棄申述受理通知書が手元に届けば、法的に相続放棄が成立し、保証債務を含む被相続人の債務を負わなくてよい立場となります。
ただし、相続放棄が成立すると次順位の相続人に相続権が移り、その方々が保証債務を引き継ぐことになります。よって、親族間で余計なトラブルが生じないよう、事前の話し合いや情報共有が大切です。
相続放棄をする際の注意点と経営者の対策
相続放棄を行うことにより、保証債務を含む債務をすべて切り離すことができますが、その一方でプラスの財産を一切受け取れなくなる点は大きなデメリットです。
したがって、被相続人の残した相続財産を正確に把握することが第一歩となります。
もう一つの注意点は、相続権が次の順位の相続人に移転することです。たとえば、子どもが相続放棄をすれば、その次の順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹など)に保証債務が移る可能性があります。
この場合、親族間で「誰が債務を引き受けるのか」「全員が相続放棄をするのか」といった調整を行うため、事前に話し合いの場を設けておくことが望ましいでしょう。
こうした親族間のトラブルは長期化しやすいため、特に注意が必要です。
経営者の立場からすると、後継者がいない場合には、相続開始後に相続人を困らせないようにするため、M&Aを検討することが一つの選択肢となります。M&Aによって会社を他社に譲渡すれば、原則として保証債務も買い手が引き継ぐことになるからです。
M&Aの成立には買い手の存在が不可欠ですが、もし買い手が見つからなかった場合には、会社を整理する方向に舵を切ることも考えなければなりません。会社を整理する方法としては、清算や破産手続きがあります。
免責とは、破産者が債務の返済義務を法的に免除されることをいいます。
通常、裁判所が免責を決定すれば、破産者は原則として破産前にあった保証債務を負担しなくてもよくなります。ただし、手続きには一定の費用と時間がかかります。
破産手続きは最終手段として検討すべきものではあるものの、「会社を続ける見込みがまったく立たない」「負債の規模が大きすぎて返済の見通しがない」といった状況では、有効な選択肢の一つです。
経営者が生きている間に破産手続きを進めることで、相続問題の発生を事前に回避できます。
経営者が急逝した際に会社の借入金や保証債務が残ってしまうと、相続人が多大な債務を負うリスクが高まってしまうのです。
まとめ
今回は、会社借入金の保証債務の相続について解説しました。
経営者保証は中小企業にとって資金調達の必須条件である一方、経営者の急逝により相続人が多額の保証債務を負うリスクがあります。生前に保証債務を整理したり、M&Aによって会社を譲渡するなどの対策を講じることで、相続人の負担を軽減することができます。また、保証債務を含めた相続財産を放棄する場合には相続放棄の手続きや期限に注意し、相続財産の調査や親族間の話し合いを十分に行うことが重要です。
弊社では、中小企業経営者の保証債務整理や相続放棄手続き支援、M&Aによる事業承継サポートを提供しています。金融機関との保証解除交渉、借入金の整理、相続開始後の迅速な財産調査と放棄申述支援など、専門家が丁寧にお手伝いします。
初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
\専門性高く幅広いニーズに素早く対応!初回無料相談はこちらから/
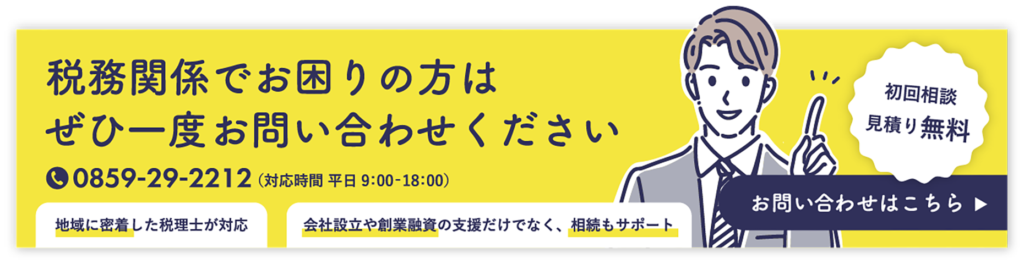
相続時の不動産に関するよくある質問
- 相続時の不動産の把握方法及び資料の収集方法は?
- 相続税申告や相続登記を行う際、どんな不動産を所有していたのかを把握することが重要です。そのために次のような方法があります。
■所有している不動産の情報を得る方法
1. 固定資産税の納付書:毎年4~5月に届く固定資産税の課税明細書には地番や土地の広さが記載されており、所有不動産を把握することができます。ただし共有名義の不動産は1名にしか納付書が届かない場合があり、全てを把握できないことがあります。
2. 登記済権利証(登記識別情報通知):固定資産税の課税対象にならない私道や墓地を所有している場合は課税明細書に記載されないため、権利証等で確認する必要があります。
3. 市区町村役場での確認:共有不動産がある場合や権利証を紛失している場合は、市区町村役場で名寄帳や固定資産評価証明書を取得することで不動産を確認できます。名寄帳には個人が所有している不動産の地番や家屋番号が記載されます。
■不動産の内容を把握した後の手続き
不動産の地番や家屋番号を把握した後は、法務局で不動産の登記簿謄本を取得します。登記簿謄本には土地の地積や所有者、抵当権の有無、建物の種類・構造・床面積などが記載されており、相続登記に必要不可欠です。
■名寄帳、固定資産評価証明書について
名寄帳は市区町村単位で発行され、不動産のある管轄の市区町村役場で取得します。申請用紙をダウンロードして郵送で請求することも可能で、共有不動産の場合は共有所有の名寄帳を発行してもらうよう伝えると漏れなく取得できます。名寄帳の名称は自治体によって「名寄帳兼課税台帳」「土地・家屋名寄帳」「土地家屋課税台帳」「固定資産課税台帳」などと異なる場合があります。固定資産評価証明書は区役所では取得できず、市役所や市税事務所で交付や郵送請求が可能です。
今回記載した内容は下記の相続通信2月号に掲載しております。