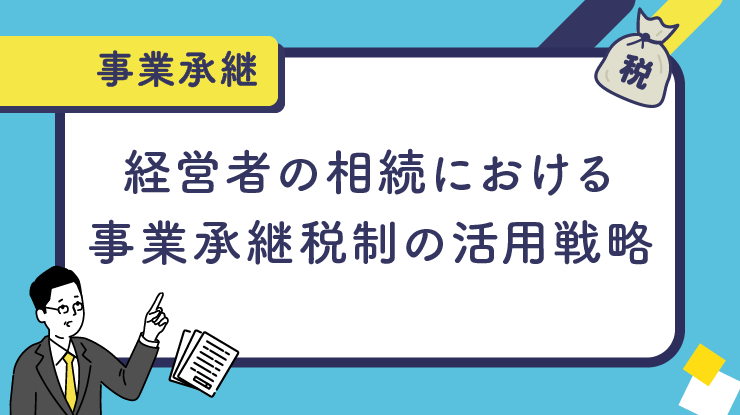事業承継は経営者にとって重要な課題です。今回は、事業承継税制の活用法を解説します。特例措置の適用期限が迫っているため、今すぐ着手しなければいけません。
\専門性高く幅広いニーズに素早く対応!初回無料相談はこちらから/
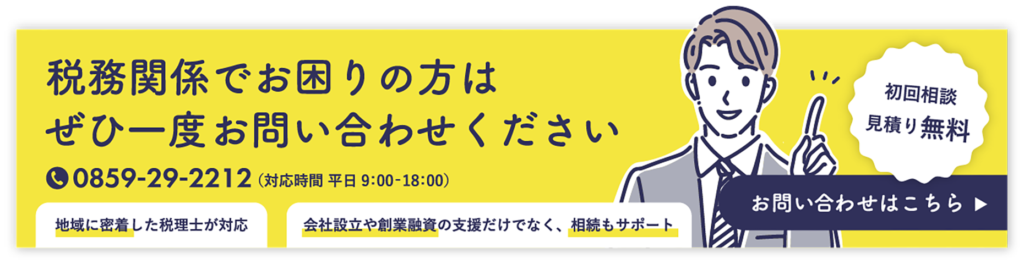
事業承継税制の概要
事業承継税制は、中小企業の円滑な事業承継を支援する制度です。非上場会社の株式を対象とし、相続税や贈与税の納税猶予を受けることができます。これにより、後継者の税負担が軽減され、事業承継を進めやすくなります。
法人版の事業承継税制の特例措置は、令和9年(2027年)12月までの期間限定で適用されます。一般措置に比べて優遇されており、納税猶予の割合は100%となります。対象となる株式の範囲も広がり、全株式が適用対象となっています。
制度の適用を受けるには、令和8年(2026年)3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出しなければなりません。この提出がなければ、特例措置を利用できません。適用要件として、経営承継円滑化法の認定を受けることが求められます。また、後継者が代表権を持ち、承継後も経営を継続しなければなりません。さらに、5年間の平均で雇用の8割以上を維持することが必要です。
特例制度の適用を受ける際には、最大3人までの後継者が対象となります。ただし、贈与の期限である令和9年12月が迫っているため、事業承継計画を早めに立てることが重要です。
期限が迫る事業承継税制の適用と対応
事業承継税制の適用を検討する企業は、特例措置が終了してしまうことを認識しなければいけません。特例承継計画の提出期限は令和8年(2026年)3月31日に設定されており、それまでに必要な準備を進める必要があります。提出期限に間に合わせるためには、後継者の決定と事業承継計画の立案を今すぐ行うことが求められます。
令和7年(2025年)の税制改正により、特例承継計画の提出時点ではなく、贈与や相続の時点で後継者が役員に就任していれば適用が可能になりました。事業承継計画の柔軟性が高まり、期限直前まで後継者の選定を遅らせることができるようになりました。ただし、贈与や相続の時点では役員であることが求められ、代表権の保有要件は引き続き維持されます。
これまでと同様に、事業承継税制の適用を受ける企業には継続的な報告義務があります。適用を受けた後も定期的に報告を行い、制度の要件を満たしていることを証明しなければなりません。これを怠ると、確定事由が発生し、猶予されていた税額の納税義務が生じるため、注意が必要です。
この制度は令和9年12月までの期間限定措置であるため、適用を希望する法人の経営者は早めの準備が不可欠です。特に、持株会社を活用する場合は、組織再編を行うこともあり、会社法の手続きに必要な期間を考慮しながら慎重に進めることが求められます。
持株会社に対する事業承継税制の適用
法人版事業承継税制は、事業会社だけでなく持株会社にも適用されます。持株会社とは、他の企業を支配する目的で株式を保有する会社のことです。事業活動を行わないため、適用要件に関して特有の留意点があります。
持株会社の株式を贈与や相続により承継する場合、対象となるのは持株会社の株式のみです。複数の事業会社の株式を直接承継する場合とは異なり、手続き上の負担は軽減されますが、持株会社の株式に対して経営承継円滑化法の認定手続きが必要となります。
持株会社は非上場株式を多く保有するため、株式等保有特定会社に該当する可能性が高くなります。この場合、純資産価額で評価されるため、後継者が贈与を受ける際の贈与税の課税価格が高くなる可能性があります。しかし、事業承継税制の適用を受けることで、贈与税は全額猶予されるため、税負担が発生することはありません。ただし、確定事由が発生した場合には、猶予されていた税額の納税義務が生じる点に注意が必要です。
また、持株会社の株式を第三者に譲渡すると、その持株会社が保有するすべての子会社の株式も確定事由に該当し、猶予されていた税額の納税義務が発生します。複数の事業会社を所有している場合、譲渡する会社と譲渡しない会社を選択することができなくなるため、慎重な対応が求められます。
特例措置の期限内であれば、最大3人までの後継者に対する贈与が可能です。しかし、特例措置が終了して一般措置に移行すると、後継者は1人に限定されることになります。持株会社に2人以上の後継者がいる場合、将来的な事業承継の計画を十分に考慮する必要があります。
持株会社が資産保有特定会社や資産運用特定会社に該当する場合、事業承継税制の適用を受けることができません。資産保有特定会社の判定においては、特定資産(現金・預金・有価証券・ゴルフ会員権など)が総資産の70%以上を占める場合に該当します。しかし、持株会社が保有する子会社のうち事業実態が認められる「特定特別関係会社」の株式は特定資産から除外され、総資産にも算入されません。そのため、子会社株式の評価額は資産保有特定会社の判定において重要な要素となります。
特定特別関係会社の事業実態の判定基準として、総収入金額が1,000万円以上であること、常時使用従業員数が5人以上であることが求められます。したがって、事業実態のない純粋持株会社であっても、子会社株式が特定資産に該当しない場合、事業承継税制の適用を受けることが可能です。
後継者が承継する際には、持株会社の代表者となることが必要ですが、可能であれば子会社の代表者となることが望ましいでしょう。持株会社の経営が安定し、子会社の事業運営にも深く関与することで、事業承継税制の適用をより確実に受けることができます。
まとめ
今回は、経営者の相続における事業承継税制の活用戦略について解説しました。
事業承継税制の特例措置は期間限定であり、特例承継計画の提出期限や後継者決定のタイミングなど、準備すべきポイントが多くあります。早めに専門家と相談し、後継者の育成や計画的な事業承継に取り組むことが重要です。持株会社を活用する場合の注意点や、事業承継税制の適用要件についても理解を深めておきましょう。
弊社では、事業承継計画の策定や事業承継税制の適用サポートを提供しています。特例承継計画の作成支援や持株会社の組織再編、後継者への株式承継に関する税務コンサルティングなど、中小企業の経営者が安心して事業を次世代へ引き継げるよう、総合的な支援を行っております。初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
\専門性高く幅広いニーズに素早く対応!初回無料相談はこちらから/
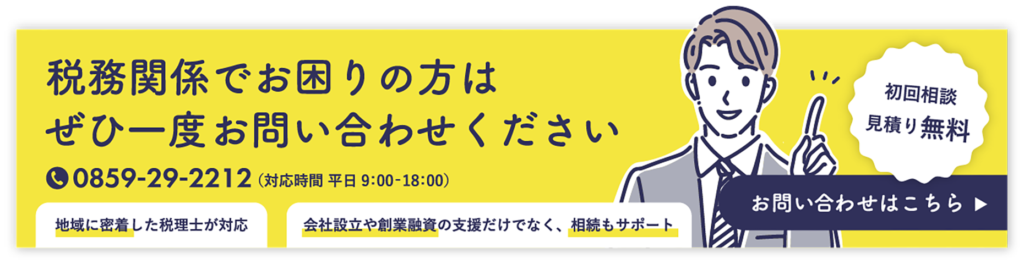
特別縁故者に関するよくある質問
- 特別縁故者とは?
- 特別縁故者とは簡単にいうと、亡くなった被相続人と特別親しい人のことをいいます。民法では以下のように定められています。
1. 被相続人と生計を同じくしていた者
2. 被相続人の療養看護に努めた者
3. その他被相続人と特別の縁故があった者
過去の判例で認められたパターンとして、内縁の妻や血縁関係のない養親、先妻・先夫またはその子、子の配偶者などが挙げられます。また、近所の人で世話や葬儀を行った者、看護師で報酬以上の働きをした者(通常の業務範囲では認められません)も該当することがあります。生計を一にせず療養看護に努めていない場合でも、被相続人の特別な信頼を受けていた者や身元引受人、精神的な支えとなっていた者などが認められたことがあります。ただし、これらの例に近いことを行っていたとしても必ず特別縁故者になれるわけではなく、家庭裁判所に申し立てを行い、その決定を受ける必要があります。 - 特別縁故者が財産を相続するまでの流れは?
- 被相続人が死亡してから特別縁故者が相続財産を相続するまでの流れは以下のとおりです。
1. 相続財産管理人の申し立て:被相続人の財産および債務を管理する相続財産管理人を家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。
2. 官報公告による相続人調査:管理人選任後、官報により公告され法定相続人の捜索が行われます。公告から6か月以内に法定相続人が見つかった場合は、その相続人が相続財産を受け取ります。
3. 被相続人の債務の支払・受遺者への遺贈:官報公告から2か月以内に法定相続人が見つからない場合、債権者や受遺者に対して公告し、請求があれば相続財産管理人が清算を行います。
4. 相続人の不存在の確定:公告から6か月経過した段階で相続人がいないことが確定されます。
5. 財産分与の申し立て:相続人不存在の確定後3か月以内に、家庭裁判所に特別縁故者に対する相続財産分与の申し立てを行います。申し立てが認められれば、特別縁故者は遺産の全部または一部を受け取ることができます。 - 遺言書で確実に財産を渡すことができる?
- より確実な方法として、遺言書を作成するという手法があります。遺言による遺贈であれば、たとえ法定相続人がいる場合でも、遺言書に記載されている財産はお世話になった方へ確実に渡すことができます(法定相続人の遺留分を除きます)。生前に作成する必要がありますが、感謝の気持ちを込めて遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
今回記載した内容は下記の相続通信3月号に掲載しております。