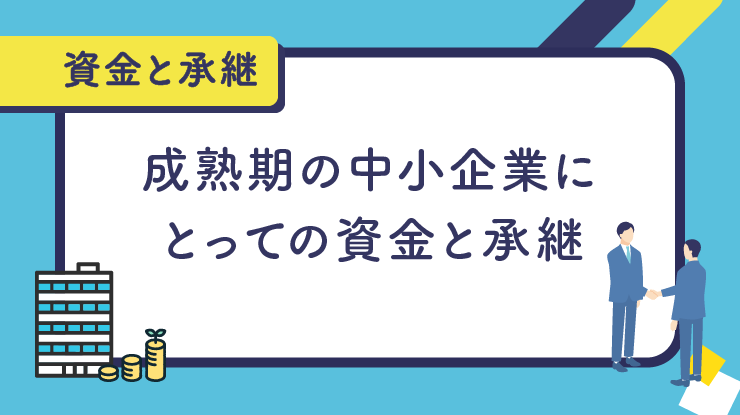成長を遂げた中小企業が次の一手を打つには、戦略的な資金調達と経営の出口戦略が不可欠です。今回は、成熟企業が直面するお金の実務について解説します。
\専門性高く幅広いニーズに素早く対応!初回無料相談はこちらから/
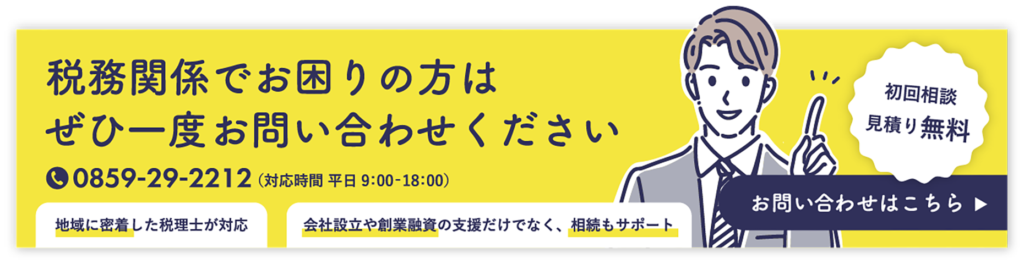
金融機関との信頼構築が生む「選択肢」
成熟期にある中小企業にとって、最も身近な資金調達先はやはり金融機関です。日本政策金融公庫や信用金庫、地方銀行が主な対象となりますが、いずれも「継続的な付き合い」が前提となるため、定期的な情報開示と信頼関係の構築が不可欠です。
たとえば、定期的に試算表や月次決算資料を提出し、業績や経営課題を率直に伝えることで、融資担当者は企業の内部事情を理解しやすくなります。これは、単なる借入の可否判断にとどまらず、「新たな資金ニーズが発生したときに迅速に対応してもらえるかどうか」という点にも大きく影響します。
また、過去の返済実績や財務の改善努力も加味されるため、毎年の決算書を「融資交渉の資料」として位置づける姿勢が重要です。中小企業の経営者の中には、必要なときにだけ金融機関を訪れる方も少なくありませんが、平時からの関係性が非常時の支援に直結するのが現実です。
加えて、信用保証協会付き融資からプロパー融資への移行も中長期的には重要なテーマです。保証付き融資は比較的通りやすい一方で、信用力向上を図る企業にとっては、保証料や保証枠の制約が成長の足かせになることもあります。自社の財務状況を客観的に分析し、プロパー融資の割合を徐々に増やすことで、将来的な選択肢が広がります。
「借りない資金調達」の現実的活用
近年は、銀行借入以外の資金調達手段にも注目が集まっています。中小企業にとっても、資金調達の多様化はもはや「選択肢の一つ」ではなく「必須の視点」と言っても過言ではありません。
その代表例が、売掛債権を活用するファクタリングです。これは、入金サイトが長い取引先が存在する場合に効果を発揮します。特に、大手企業との取引が多い下請け企業では、請求から入金までに60日以上かかることもあり、資金繰りが逼迫しがちです。ファクタリングを活用すれば、売掛金を早期に現金化でき、仕入れや人件費などの先行投資に充当することが可能です。
また、近年増加しているのがクラウドファンディング型の資金調達です。地域活性や新商品開発など、社会性や話題性のあるプロジェクトでは、資金だけでなく販路や顧客の獲得にもつながる効果があります。とくに地場の飲食店や工芸品メーカーなど、ブランド力の強化を図りたい中小企業にとっては、宣伝効果と資金調達を同時に得られる手段として有効です。
さらに、最近では補助金や助成金の活用も欠かせません。中小企業庁が提供する「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」などは、適切な活用により1,000万円を超える支援を受けられる場合もあります。ただし、書類作成や審査対応に手間がかかるため、専門家の支援を受けながら進めることが一般的です。
他方で、リースやレンタルといったオフバランス型の手法も再評価されています。設備投資に多額の初期費用を要する場合でも、リースを活用すればキャッシュフローを守りながら導入が可能です。とりわけIT機器や車両など、使用頻度や技術変化の速い分野では有効な手段となります。
成熟期こそ「内部留保」と「出口戦略」の視点を
企業が成熟期に入ると、日々の資金繰りだけでなく、将来を見据えた資金戦略が求められます。とくに、内部留保の使い方、経営者の引退に伴う事業承継、そして最終的な出口戦略を三位一体で考える視点が重要となります。
内部留保については、単に現金を手元に置いておくだけではなく、計画的な活用が必要です。インフレや法人税率の改正などの影響を受けて、現金の価値は徐々に目減りしていきます。老朽化した設備の更新、新規事業への投資、人材教育への資金投入など、次の成長のために内部留保を積極的に活用する姿勢が求められます。
出口戦略として最も注目されているのがM&Aです。中小企業にとっても、廃業という選択を避けるために、第三者への事業承継が現実的な手段となっています。中小企業庁や都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターでは、買収を希望する企業とのマッチングや譲渡スキームのアドバイスを提供しており、利用者が急増しています。
譲渡によって得られた資金は、経営者個人の資産形成のほか、次世代へ承継する相続財産としての意味も持ちます。このため、M&Aと相続対策は密接に関係しています。自社株の評価を意識したタイミングでの譲渡、譲渡益にかかる税負担の軽減、退職金の最適な設計などを事前に検討しておくことで、老後資金の確保と相続対策の両立が可能になります。
親族内承継を選ぶ場合にも、金融機関の理解を得た資金計画が不可欠です。後継者への株式譲渡や贈与に関しては、相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)を活用することで、大幅な納税猶予が可能となります。ただし、制度の適用には厳格な要件と間近に迫る期限があるため、税理士や認定支援機関のサポートが必須です。
一方、親族内に後継者がいないケースでは、従業員承継や外部経営者の招聘(社外承継)も検討の余地があります。この場合、資金調達の観点からは「経営者保証の解除」や「役員貸付金の整理」といった課題が生じやすく、事前準備が重要となります。
このように、成熟期における資金調達は、単なる運転資金や設備投資の確保にとどまらず、将来の経営の方向性と事業承継に密接に結びついています。内部留保の戦略的活用、出口戦略としてのM&A、そして経営者の引退と家族の未来を見据えた相続と事業承継の計画を立案しましょう。これらを包括的に考えることが、企業の永続的な存続可能性を高める鍵となります。
まとめ
今回は、成熟期の中小企業が直面する資金調達と承継のポイントについて解説しました。
金融機関との信頼構築により選択肢を広げることや、ファクタリングやクラウドファンディング、補助金・助成金、リースなど多様な資金調達手段の活用、内部留保の戦略的運用、出口戦略としてのM&Aや親族内承継・社外承継の準備が重要です。
弊社では、中小企業の資金調達や事業承継に関するサポートを提供しています。金融機関との交渉資料の整備やファクタリング・補助金等の資金調達手法のご相談、M&Aや親族内承継といった出口戦略のご提案など、企業の成長ステージに応じた資金計画をお手伝いします。初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
素早く対応!初回無料相談はこちらから/
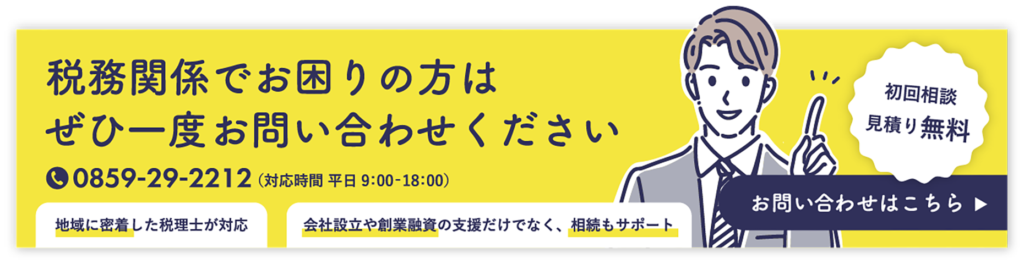
埋葬費・埋葬料に関するよくある質問
- 埋葬費・埋葬料の違いについて教えてください。
- 埋葬費とは、社会保険組合(組合健保、共済組合、協会けんぽ)に加入している被保険者と生計維持関係にない人が葬儀を行った際に支給される給付金です。亡くなった人の収入で生活をしていない人が葬儀をした場合に貰えるのが埋葬費で、給付額は葬儀費用に実際にかかった額(上限5万円)となります。
一方、埋葬料は亡くなった人の収入で生活をしている人が葬儀を行った場合に支給される給付金で、金額は一律5万円です。申請期限は、埋葬費が葬儀日から2年以内、埋葬料が死亡の翌日から2年以内と、起算日に違いがある点に注意してください。また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた人の葬儀では葬祭費という給付金が支給されますが、支給額や申請期限は保険の種類や市区町村ごとに異なります。 - 葬費・埋葬料が支給される条件とは?
- 埋葬費と埋葬料には支給条件があります。まず埋葬費は、実際に葬儀を行った人に支給する制度であるため、葬儀を行っていない場合は支給されません。ただし、火葬のみの直葬でも葬儀を行ったと判定されるため、5万円を上限に支給されます。埋葬料は、葬儀を行っていなくても死亡の事実が確認できれば支給されますが、業務上や通勤途上で亡くなった場合は労災保険の対象となり埋葬費・埋葬料の対象外です。
また、時効後に申請した場合は支給されませんので、申請期限に注意が必要です。被保険者が退職などで資格を消失した後でも、資格喪失後3カ月以内に亡くなった場合は支給対象となります。 - 葬費・埋葬料の請求手続きについて教えてください。
- 埋葬費や埋葬料は葬儀を行えば自動的に支給されるものではなく、申請が必要です。申請先は故人が加入していた健康保険組合で、国民健康保険に加入していた場合は役所に請求します。必要書類や申請手続きについては加入していた保険や自治体ごとに異なりますので、詳細は各窓口に確認しましょう。
今回記載した内容は下記の相続通信4月号に掲載しております。