合併はシナジー効果創出や生産性向上、事業承継対策などの経営課題を解決する有効手段です。中小企業が単独では困難な成長と効率化を達成するための重要な選択肢となります。今回は合併の実務について説明します。
\専門性高く幅広いニーズに素早く対応!初回無料相談はこちらから/
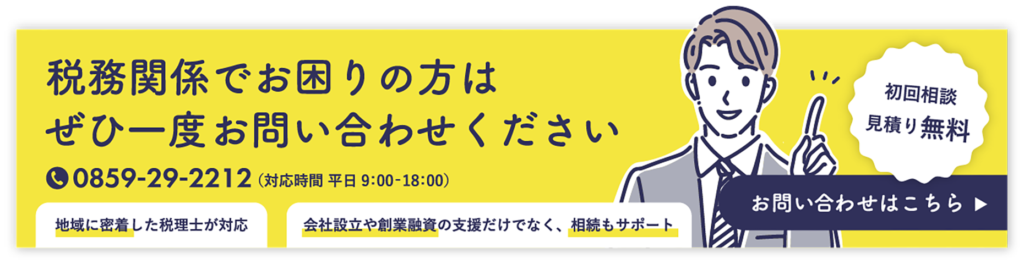
合併による経営統合の目的とメリット
企業が合併を選択する最大の理由の一つが「シナジー効果」の創出です。シナジー効果とは、二つの会社が統合することで、単独では得られない価値や効果を生み出すことを意味します。
例えば、営業地域や顧客層が異なる企業同士が合併することで、市場シェアを拡大できます。また、互いの技術力やノウハウを共有することで、新たな製品・サービスの開発が可能になることもあります。
特に中小企業においては、経営資源の限界を超えるための選択肢として合併が有効です。
例えば、製造業であれば生産設備の共有によって稼働率を向上させることができますし、IT企業であれば開発リソースの集約によって大規模プロジェクトの受注が可能になるといった効果が期待できます。
合併によって、間接部門の統合や重複業務の削減など、経営の効率化を図ることができます。特に管理部門や物流システムの統合によるコスト削減効果は大きいと言えるでしょう。また、規模の拡大によって仕入れや物流のスケールメリットを享受できるようになることも、合併の重要な目的の一つです。
現在のように人材確保が困難な経営環境においては、限られた人材を効果的に活用するための手段としても、合併は有効な戦略となります。業務の集約によって一人あたりの生産性を高めることで、人材不足という経営課題の解決にもつながるのです。
近年、経営者の高齢化に伴う事業承継問題が顕在化していますが、合併は事業承継の有効な解決策の一つとなります。自社に適切な後継者がいない場合、信頼できる企業と合併することで、事業の継続性を確保しつつ、円滑な承継を実現できます。
また、合併によって企業規模が拡大することで、優秀な人材を確保しやすくなり、将来的な経営幹部の育成にもつながります。さらに、合併存続会社が上場会社であれば、交付される株式は容易に現金化できるため、相続対策としても一定の効果が期待できます。
合併の基本構造と実務手続き
合併には「吸収合併」と「新設合併」がありますが、一般的なM&Aでは吸収合併が採用されることが多くなっています。
吸収合併とは、一方の会社(消滅会社)の権利義務の全部を他方の会社(存続会社)が承継する方法です。吸収合併を活用する主なメリットとしては、包括的な承継が行われることで個々の資産や負債、従業員に関する個別の手続きが原則として不要になり、事務負担が軽減される点が挙げられます。
また、税務上の取扱いにおいても、適格要件を満たすことでみなし配当が発生せず、資産移動に係る税負担を抑えることができます。合併は法的手続きの簡便さと税務上のメリットを兼ね備えた統合手法と言えるでしょう。
合併において重要なのが「合併比率」の算定です。これは消滅会社の旧株式1株に対して、存続会社の株式を何株割り当てるかという比率です。この算定には、両社の株式の評価額が基礎となります。評価方法としては、時価純資産による評価が多く用いられます。
合併を実行するための実務手続きは多岐にわたります。まず両社間で吸収合併契約を締結します。会社法では、合併契約において定めるべき事項が規定されており、これに沿った内容で契約を締結する必要があります。
契約締結後は、合併契約備置開始日から吸収合併の効力発生日後6ヶ月を経過する日までの間、合併契約の内容等を記載した書面を本店に備え置かなければなりません。これは株主や債権者の閲覧に供するためのものです。
次に、消滅会社は効力発生日の前日までに株主総会の特別決議によって合併契約の承認を受ける必要があります。株主総会を招集する際は、株主総会の日の2週間前までに株主に対して通知をしなければなりません。
株主総会での承認後は、個別通知と公告によって債権者保護手続きを行い、最終的には消滅会社が吸収合併の効力発生日から2週間以内に本店所在地において解散の登記をすることで、法的な手続きが完了します。
合併の税務上の取扱いと重要ポイント
合併における税務上の取扱いは、適格合併か非適格合併かによって大きく異なります。適格合併の場合、株式の譲渡益課税およびみなし配当課税は発生せず、資産・負債は帳簿価額で引き継がれます。
一方、非適格合併の場合、現金を交付しない場合でもみなし配当課税が発生し、現金を交付する場合は株式の譲渡益課税も加わります。
適格合併となるための要件は、両社の持株関係によって異なります。持株関係が100%の場合は他の要件に関わらず税制適格となります。持株関係が50%超の場合は、従業者の引継ぎが80%以上であることと、事業が継続して営まれることの2つの要件を満たす必要があります。
さらに、持株関係が50%未満の場合は、事業関連性、事業規模または特定役員の引継ぎ、従業者引継ぎ、事業継続、株式継続保有という5つの要件を全て満たさなければなりません。これらの要件を満たさない場合、非適格合併となり税務上の負担が増加するため、事前の検討が重要です。
合併において特に注目すべきは繰越欠損金の取扱いです。適格合併の場合、消滅会社の繰越欠損金を存続会社に引き継ぐことが認められていますが、無制限に許容されているわけではありません。
繰越欠損金の引継ぎには厳格な要件が定められており、両社の繰越欠損金を合併後も使用できるかどうかが、合併スキーム選択の重要なポイントとなります。
(著者 公認会計士/税理士 岸田康雄)
まとめ
今回は、経営統合(合併)のしくみと実務について解説しました。
弊社では、生前に行う相続対策サポートを行っています。
生前から相続税のシミュレーションを行っておくことで、余裕をもったプランニングを行うことができ、次の世代に安心して財産を残すことができます。
初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
\専門性高く幅広いニーズに素早く対応!初回無料相談はこちらから/
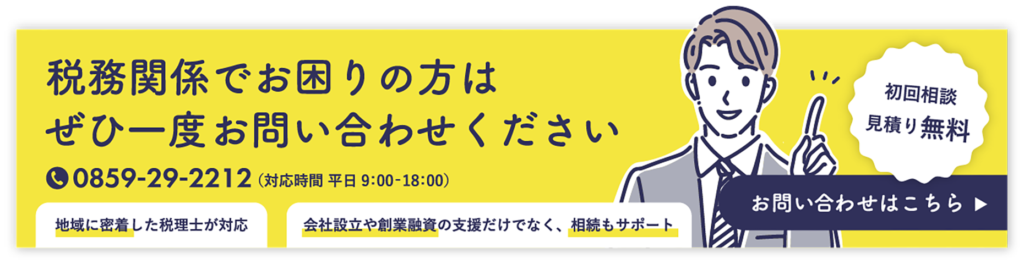
遺産分割協議書に関するよくある質問
- 遺産分割協議書とは?
- 被相続人が遺言や死因贈与により、具体的にどの財産を誰に引き継がせるかを決めずに亡くなった場合、遺産は相続人(配偶者や子供など)に相続され、被相続人全員の共有になります。相続人は、遺産分割という手続きを取り、共有財産を各相続人に分配することができます。遺産分割協議書とは、遺産分割につき全ての相続人が協議して合意した内容を記載した文書をいいます。
遺産分割協議書を作成する目的の一つは、合意した内容を明確に記載しておくことにより、後の争いを避けることにあります。また、不動産や預貯金、株式、自動車などの名義を変更する場合、遺産分割協議書の提出を求められます。
遺産分割協議は、全相続人が参加して行う必要があります。長い間付き合いがないからといって、特定の相続人を協議に加えずに、遺産分割協議書を作っても、後に、同人から無効主張されて、争いの原因となります。遺産分割協議は、全相続人を参加させ、全員の合意を取ることが肝要です。
その前提として、相続人は誰なのかを特定する必要があります。相続人調査は、被相続人の現在及び過去の戸籍(改製原戸籍)を出生までさかのぼって取り寄せて、自分たちのほかに相続人がいないかを確認します。戸籍を調査することにより、それまでは知らなかった先妻との子や認知した子が見つかる場合があります。
また、遺産分割の前提として、被相続人の財産には何があるのかを確定する必要があります。遺産には、預金や不動産などの財産のほか、借金や未払金などの負債もあります。まず、財産及び負債をできる限り洗い出すことが重要です。被相続人の自宅や貸金庫などを調査して、銀行通帳や土地建物の登記簿謄本、契約書や証券類などが見つかることもありますし、親戚や友人の話から財産が見つかることもあります。また、パソコンやスマートフォンなどにも情報が保存されているかもしれません。 - 遺産分割協議書の作成方法について教えて下さい。
- 全相続人間で協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、協議の内容をすべて記載しておきます。
もっとも、例えば、銀行には、土地の分割について知らせたくないなどの事情がある場合には、銀行預金に関するものと土地に関するものを、別々の遺産分割協議書として作成することもできます。遺産分割協議書は、手書きでも、パソコンで作成しても構いません。
相続人の確定手続きが複雑な場合もありますし、遺産分割協議書に不備があると、不動産の登記などができなかったり、遺産分割の内容によっては、相続税の額が変わったりする場合がありますので、注意が必要です。不動産や自動車の特定は、全部事項証明書や車検証の書面通りに記載しておかないと登記登録が受け付けられない場合があるのでご留意ください。
今回記載した内容は下記の相続通信5月号に掲載しております。
