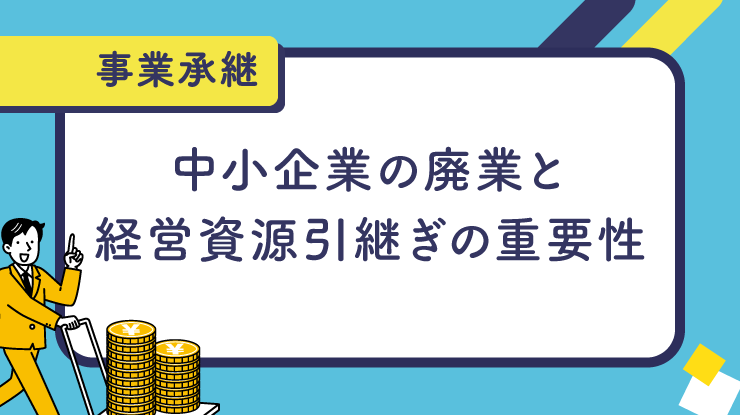中小企業の廃業が増え、経営資源の喪失が社会的損失となっています。事業承継では「経営資源引継ぎ」を進め、生産性向上を図ることが重要です。ここでは、その問題について解説します。
\専門性高く幅広いニーズに素早く対応!初回無料相談はこちらから/
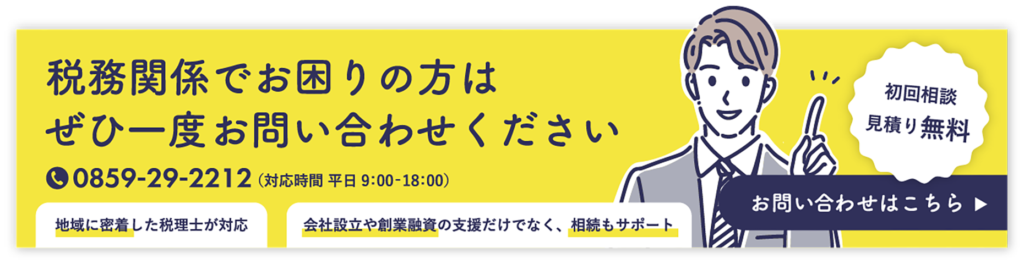
中小企業における廃業の現状と課題
日本の中小企業は、長年にわたり経済成長を支えてきましたが、経営者の高齢化や後継者不足が原因で、企業の存続が厳しい状況に追い込まれています。帝国データバンクによると、2022年には全国で約5万3千件の休廃業・解散が報告され、特に注目すべきは、これらのうち54%が黒字廃業であった点です。
黒字廃業とは、事業が経済的に安定しているにもかかわらず、経営者が今後の経済環境や自社の将来に対して悲観的な見通しを持ち、自ら廃業や解散を選択するケースを指します。
これにより、経営資源が失われるリスクが発生し、地域や経済全体に対する損失も避けられません。特に問題となるのは、企業が持つ知的資産、すなわち顧客関係や技術、ノウハウなど、価値ある資源が適切に引継がれないことで、これらが失われてしまうケースが多い点です。
廃業に伴い消失する可能性があるこれらの資産は、事業の成長や維持に不可欠であり、社会にとっても大きな損失をもたらす可能性があります。現状では、行政機関や金融機関、さらに専門家による支援が行われているものの、これらの支援策の多くは事業の収益性を向上させるものではなく、単なる延命措置に留まっています。
例えば、行政による持続化補助金の支給や、金融機関による無利子無担保の緊急融資(いわゆるゼロゼロ融資)は、中小企業の長期的な存続を実現するための実質的な改善策とは言えず、事実上、経営者を無理に働かせ続けるだけの手段となっている場合が少なくありません。
これにより、業績悪化が続く中、資金が尽きるのは時間の問題となり、中小企業の構造的な課題解決には至っていないのです。
経営資源の集約と生産性向上のための実践的アプローチ
中小企業の多くは、高齢化した経営者にとって事業の生産性向上や賃上げ、最新のデジタル技術導入に必要なIT投資を行うための体力や資金力が乏しいことが大きな課題となっています。
生産性を抜本的に改善するためには、同業他社との経営資源の集約を図り、事業規模を拡大することが有効な手段と考えられています。経営資源の集約は、企業が保有する価値ある資産(従業員、顧客関係、技術やノウハウなど)を他社に引き継ぎ、より大きな事業体を構築することで、資源を効率的に活用することが可能となり、生産性向上を実現することができます。
事例として、従業員10人規模の企業3社がそれぞれ単独で存続する場合と、これら3社の経営資源が集約され、30人規模の一つの企業として統合される場合の2つのケースを考えてみましょう。もし3社が単独で生き残る場合、それぞれが限られた資源の中で経営を続ける必要があり、生産性向上の余地が限られます。
しかし、経営資源が統合されると、同じ30人の従業員を擁しながらも、規模の経済が働くことによって、間接費や営業コストが削減され、結果的に生産性が向上するのです。
例えば、本社経費や人材採用、教育費用、広告宣伝費などの間接コストが削減され、より効率的な経営が可能となります。このような規模の拡大によるコスト削減効果は、最終的に従業員の賃上げやIT投資のための財源確保にもつながり、企業の競争力強化と持続的成長が期待されます。
また、価値ある経営資源のみを引き継ぐ選択肢も重要です。企業の吸収合併や事業譲渡の際、企業全体をそのまま引き継ぐのではなく、従業員や顧客関係といった重要な要素に絞って引継ぐことで、企業全体の効率性が向上し、無駄な負担を避けることができます。
したがって、中小企業が持続的に成長するためには、行政や金融機関の支援が必要であり、同時に、経営資源の適切な引継ぎや集約を進めることが不可欠です。
適切な経営資源引継ぎの方法とその選択肢
日本における中小企業支援に関する議論では、「事業承継」という表現が一般的に使われていますが、実際に求められているのは事業そのものの承継ではなく、経営資源の効果的な引継ぎです。経営資源には、従業員や後継者、設備、資金、情報などが含まれ、これらを個別に引き継ぐことが事業承継以上に求められている実態があります。
具体的には、事業承継の中で重要なのは、会社全体を引き継ぐことよりも、必要な経営資源を効率的に引継ぐことに重点を置くべきだということです。
例えば、個人事業者が法人としての「箱」をそのまま引き継ぐケースと、事業のみに関連する重要な経営資源のみを引き継ぐケースが存在します。法人ごと譲渡すると、不必要な資産や債務も含まれるめ、新たに引き継ぐ側の負担が増えるリスクがあります。
これに対して、必要な資源のみを引き継ぐ形態、すなわち「事業譲渡」や「経営資源引継ぎ」を選択することで、無駄な資産やリスク要因を排除し、より軽量で柔軟な事業運営が可能となります。
例えば、価値のある顧客関係や従業員といった経営資源を優先的に引き継ぐことで、事業の成否に影響を与える重要な要素を確保でき、譲受側にとってもリスクが低減されます。
また、知的資産である顧客関係や技術、ノウハウなどを適切に承継することは、単なる法人譲渡や事業承継と異なり、事業の再生や新たな展開に必要不可欠です。
譲受側は、これらの知的資産を活用することで、事業をスムーズに継続させることができるだけでなく、新しいビジネスチャンスの創出にもつながります。経営資源引継ぎの適切な実行により、事業が廃業することなく持続可能な形で維持されるとともに、長期的な日本経済の成長に貢献することが期待されます。
(著者 公認会計士/税理士 岸田康雄)
まとめ
今回は、中小企業の廃業と経営資源引継ぎ問題について解説しました。
弊社では、生前に行う相続対策サポートを行っています。
生前から相続税のシミュレーションを行っておくことで、余裕をもったプランニングを行うことができ、次の世代に安心して財産を残すことができます。
初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
\専門性高く幅広いニーズに素早く対応!初回無料相談はこちらから/
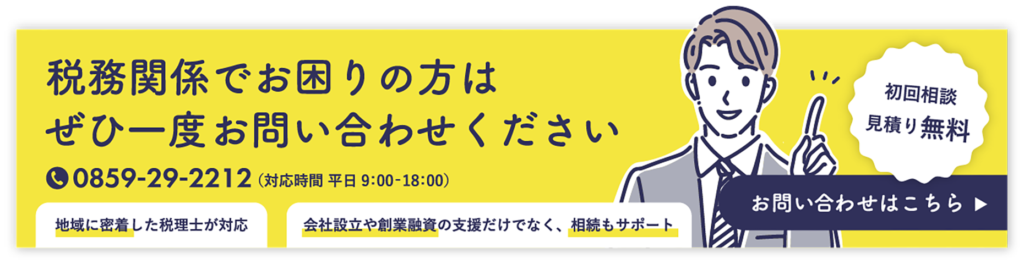
相続に関するよくある質問
- 公証役場の遺言検索システムの活用方法について教えて下さい。
- 公証役場の遺言検索システムは、公正証書遺言がデータベース化されたものです。1989年以降に作成された遺言の情報が登録されており、全国どこの公証役場からでも検索できます。遺言書の作成日、証書番号、遺言者の氏名などが含まれており、検索は無料です。
遺言書が見つかれば、保管している公証役場で謄本を発行してもらえます。検索できるのは相続人などの利害関係者で、遺言者が亡くなる前は遺言者本人のみです。
また、検索には、戸籍謄本や本人確認書類などが必要です。特に注意しておきたい点は、相続人の代理人や代襲相続人、受遺者が検索するケースです。委任状などそれぞれ追加の書類が必要ですので、公証役場に出向く際には、二度手間にならないように、必要な書類を忘れずに持参するよう気を付けましょう。
今回記載した内容は下記の相続通信11月号に掲載しております。