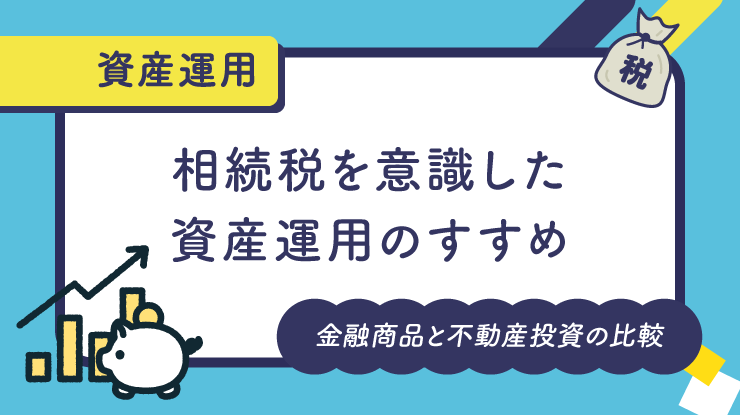日本人の資産運用は銀行預金が中心ですが、相続税を考慮すると金融商品は税負担が重く、不動産は税負担が軽くなります。今回は相続税を考慮した資産運用の戦略を解説します。
\専門性高く幅広いニーズに素早く対応!初回無料相談はこちらから/
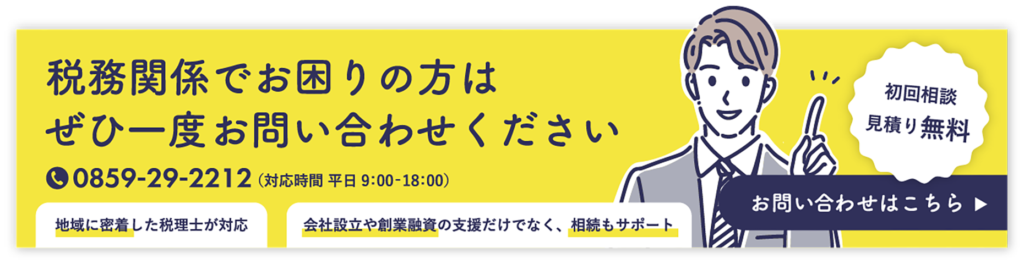
日本人の貯蓄文化と「貯蓄から投資へ」の課題
日本人は古くから「貯蓄が美徳」と考えてきました。多くの方が給料や収入を銀行に預け、確実にお金を守る手段として利用しています。
しかし、インフレ(物価の上昇)によるお金の価値の目減りや、利率の低さを考えると、銀行預金は資産を「増やす」手段としては不適切です。近年、政府は「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げ、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を通じて金融商品への投資を促進しています。
これらの制度は投資の利益が非課税になるなどのメリットがありますが、全体的には日本人の投資意欲はまだ低い状態です。例えば、2022 年のデータによると、日本人の家計金融資産の約 54%が銀行預金に偏っており、米国の約 13%と比較しても貯蓄志向が強いことが分かります。
一方で、株式や投資信託などの金融商品に資産を配分する割合は日本では 20%以下であり、米国の 50%超に比べて大きな差があります。このデータが示すように、日本では「貯蓄する文化」が根強く残っているのです。
相続税の視点から見ると、銀行預金も金融商品も同じ評価額として計算され、課される税負担が重くなります。つまり、銀行預金を多く保有している場合、相続時にその大部分が税金として消えてしまうリスクがあるのです。この問題を考えると、「資産を守る」だけでなく「減らさない」運用方法を検討する必要があると言えるでしょう。
金融商品と不動産投資の違い
金融商品とは株式、投資信託、債券などの金融市場で取引される資産を指します。これらは「ハイリスク・ハイリターン」の特性を持ち、投資した金額が大きく増える可能性がある一方で、大きく減少するリスクも伴います。
例えば、ある高齢者が「年利 5%」を謳った投資信託に 1 億円を投資したとしましょう。この場合、年間 500 万円の利回りが期待できます。しかし、投資信託の価格が下落したり、為替変動リスクが発生したりする可能性もあり、元本が大きく減少するリスクも考慮する必要があります。
さらに、相続時にはこの 1 億円がそのまま相続財産として評価され、多額の相続税が発生します。
一方、不動産投資は「ローリスク・ローリターン」の特性を持ちます。不動産投資とは、土地や建物を購入し、その賃貸収入や資産価値の上昇を通じて利益を得る手法です。不動産の最大の特徴は、相続税評価額が大幅に引き下げられることにあります。
例えば、1 億円のマンションを購入した場合、その相続税評価額は約 6,000 万円まで引き下げられるケースが一般的です。さらに、借入金を利用して不動産を購入した場合、借入金額が財産から差し引かれるため、相続税がゼロになることもあります。加えて、小規模宅地の特例を適用することで、評価額をさらに下げることが可能です。
このように、金融商品は高いリターンを得られる反面、相続税の負担が重く、不動産のリターンは控えめですが、相続税負担を大幅に軽減できるという違いがあります。
相続税を見据えた「世代を超えた資産運用」のすすめ
資産運用を考える際、特に相続が視野に入ってくる高齢者にとって重要なのは「世代を超えた資産運用」です。つまり、自分の世代だけでなく、次世代にどのように資産を引き継ぐかを考えることが必要です。
例えば、10 億円の銀行預金を持っているケースを考えてみましょう。相続税は約 4 億円発生し、相続後に残る金額は税引後で 6 億円になります。
一方で、同じ 10 億円を不動産に投資していた場合、不動産の評価額が相続には大幅に引き下げられるため、相続税は約 1 億円に抑えられます。この場合、税引後に残る金額は 9 億円となり、銀行預金よりも 3 億円多く資産を残せるのです。
極端な例として、大地震が発生し不動産価格が大きく下落した場合を考えてみます。不動産の価値が 3 億円減少したとしても、残る資産の価値は約 6 億円となります。金融資産で相続した場合の金額と変わりません。
この計算例からも分かるように、銀行預金は相続税負担が重く、不動産は相続税負担の軽減効果が大きいため、相続時の手残り額で見ると明らかに有利な選択肢となります。
日本には相続税が存在するため、資産運用は「増やす」だけでなく「減らさない」視点を持つことが重要です。若年期には金融商品で積極的に資産を増やし、相続が近づく高齢期には不動産で資産を守るという戦略が理想的です。
このような戦略を取ることで、次世代により多くの資産を引き継ぐことが可能になります。筆者が税理士として多くの相続案件を担当する中で、金融資産の相続税負担に苦しむ方は少なくありません。
一方で、不動産投資を行い、適切な相続税対策を講じた方々は、次世代に大きな財産を引き継ぐことに成功しています。
なお、不動産の価格変動リスクを過大に心配する方がいますが、確実に発生する相続税の現金流出と比較すれば、そのリスクは微々たるものです。日本独自の税制を理解し、家族のための資産運用を計画していくことが、これからの時代に求められる視点ではないでしょうか。
このように、相続税を見据えた資産運用の選択肢を検討することで、よりよい未来を築くことが可能になります。今一度、あなたの資産運用の方針を見直してみてはいかがでしょうか。
(著者 公認会計士/税理士 岸田康雄)

まとめ
今回は、相続税を考慮した資産運用の戦略について解説しました。
弊社では、生前に行う相続対策サポートを行っています。
生前から相続税のシミュレーションを行っておくことで、余裕をもったプランニングを行うことができ、次の世代に安心して財産を残すことができます。
初回のご相談・お見積りは無料です。弊社の経験豊富な税理士が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
\専門性高く幅広いニーズに素早く対応!初回無料相談はこちらから/
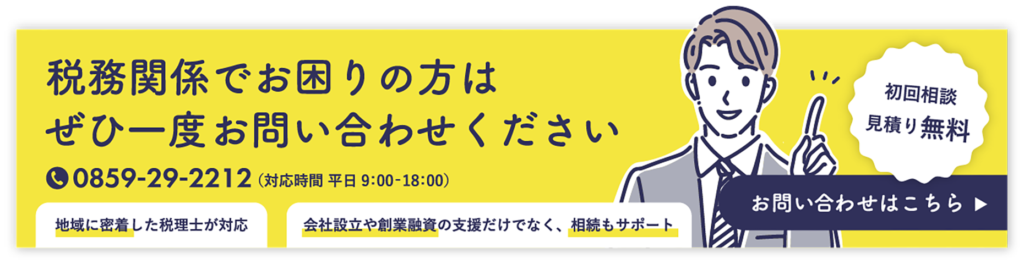
相続に関するよくある質問
- 代表相続人の選出と役割について教えて下さい。
- 代表相続人は、税務署の相続税支払いや、金融機関での遺産口座解約などを代表して行います。代表相続人とは、相続人が複数いる場合に、相続手続きを代表して行う人のことです。全ての手続きを同じ人が行う必要はなく、税務申告や金融機関の手続きなど、手続きごとに別の代表相続人を立てることも可能です。
代表相続人適任者の選び方に関しては、相続人であれば誰でも代表相続人になることができ、代表相続人になるための優先順位もありません。特に取り決めはありませんが、一般的に相続人同士の話し合いで代表相続人を選ぶのが良いでしょう。
今回記載した内容は下記の相続通信12月号に掲載しております。